土留めとは何?意味・工法や使用される材料をやさしく解説

「土留め(どどめ)」という言葉、普段の生活ではあまり耳にしないかもしれません。でも実は、公園の花壇やお庭、道路沿いの歩道など、私たちの暮らしの身近な場所で活躍しています。
今回は、「土留めとは何か?」というテーマで、役割や種類、使われる材料についてわかりやすくご紹介します。そして最後に、テック大洋工業が手掛ける耐候性鋼材の土留め「鋼板壁」の魅力と、実際の施工事例もご紹介します。
土留めとは?暮らしの安全と景観を守る構造物

土留めとは、雨や風で土が崩れたり流れたりするのを防ぐために設置される構造物のことです。特に土地に段差がある場所や、建物を建てるときの基礎工事では欠かせません。
また土留めは、景観を整える目的でも使われます。例えば、園芸用の花壇や庭を作る際にも土留めが使われることで、美しく整った形が保たれ、植物の根も安定して育つことができます。
土留めの役割
土砂の流出防止
雨や風、地震などの自然現象で土が崩れたり流れたりするのを防ぎます。土が動くことで周囲の土地や建物に被害を及ぼすことがあるので、それを防ぐために土留めが必要です。
土地の形状を保つ
土地を段階的に区切ることができるため、段差がある土地を活用しやすくします。これにより、住宅地や公園、商業施設などでの土地利用が効率的になります。
美観の維持
土が無秩序に流れたり崩れたりするのを防ぎ、景観を守る役割も担っています。特に公共施設や商業施設など、見た目を重視するところで多く活用されています。
活用される場面
- 公園の斜面や植栽を守る
- 家の庭で花壇を作るとき
- 道路や歩道の安全を保つ
土留めがあることで、土砂が流れ出すのを防ぎ、周囲の環境や建物の安全を守ります。
擁壁(ようへき)との違いは?
「土留め」と似た言葉に「擁壁(ようへき)」があります。どちらも土砂の崩れを防ぐ役割がありますが、次のような違いがあります。
土留め
広い意味で土砂を支えるすべての工事や構造物を指します。仮設的なものも含みます。
擁壁
コンクリートや石などで作られる恒久的な壁状の構造物。高さ2mを超えるものは建築基準法の規制対象となり、確認申請や構造計算が必要。
つまり、擁壁は土留めの一種です。
土留めに使われる材料は色々
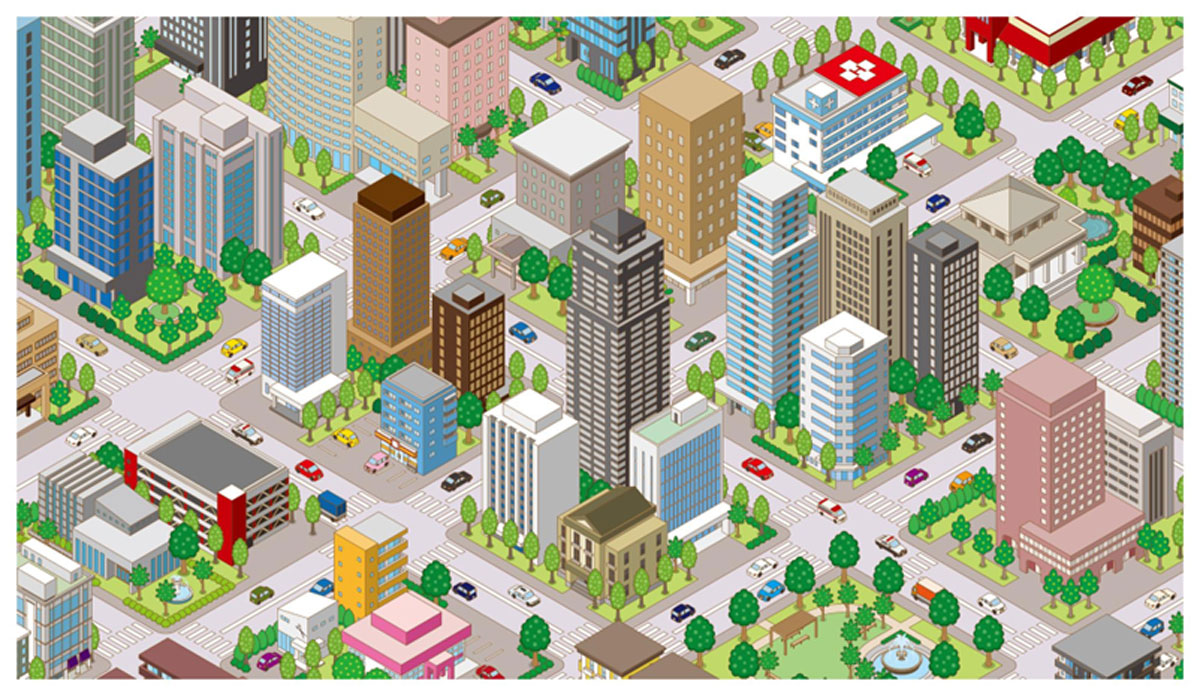
土留めに使われる材料にはさまざまな種類があり、設置する場所や目的によって最適な素材があります。
コンクリート
強度と耐久性に優れ、住宅地の造成や擁壁に広く使われています。
長期間、安定した構造を維持できるため、住宅地や公共インフラには欠かせない素材ですが、施工や設計には専門性が必要です。
ブロック・石材
ブロックは比較的施工が容易で整った外観をつくりやすく、石材は自然の風合いを活かせるため景観を重視する場所に適しています。
木材
加工しやすく温かみのある雰囲気を感じられるので、花壇や小さな庭で手軽に使われることが多い素材です。ただし耐久性は低めです。
鋼材
強度の高いH形鋼や矢板など、短期間で確実に土を支えるため工事現場など高強度が必要な場面で使われています。腐食の問題があるので一時的な利用や仮設構造物などに適しています。
耐候性鋼材(たいこうせいこうざい)
表面にできる錆(さび)の皮膜が内部の腐食を防ぐ特別な鋼材。塗装なしでも長持ちし、環境への負荷も少ない注目の素材です。独特な風合いは景観素材としても優れ、サステナブルな素材としての需要も増えています。
テック大洋工業の「鋼板壁」
景観と機能を両立する次世代の土留め
テック大洋工業が開発した「鋼板壁」は、耐候性鋼材を使用した土留め製品です。これまでの土留めに比べて、次のような特長があります。
長持ちで環境にもやさしい
耐候性鋼材の特性により、塗装が不要でメンテナンスの手間も少なく、長期間美しい外観を保てます。
デザイン性の高さ
スリムで直線的なデザインが特徴。公園や商業施設などでも景観を損なわず、むしろ引き立てます。
施工がスピーディ
軽量で扱いやすい鋼板は、現場での施工がスムーズ。複雑な形状にも柔軟に対応できます。
実際の施工事例
安全で美しい空間づくりに「鋼板壁」を
土留めは、私たちの暮らしを支える縁の下の力持ち。そこに景観性や環境への配慮を加えたのが、テック大洋工業の「鋼板壁」です。
公園・商業施設・住宅地など幅広い場所で採用され、これからの街づくりに新しい価値を提供します。


